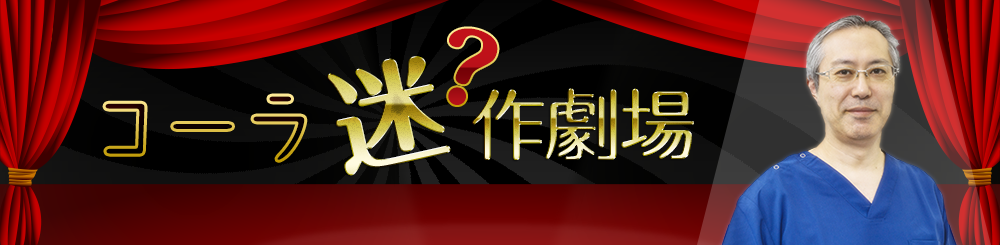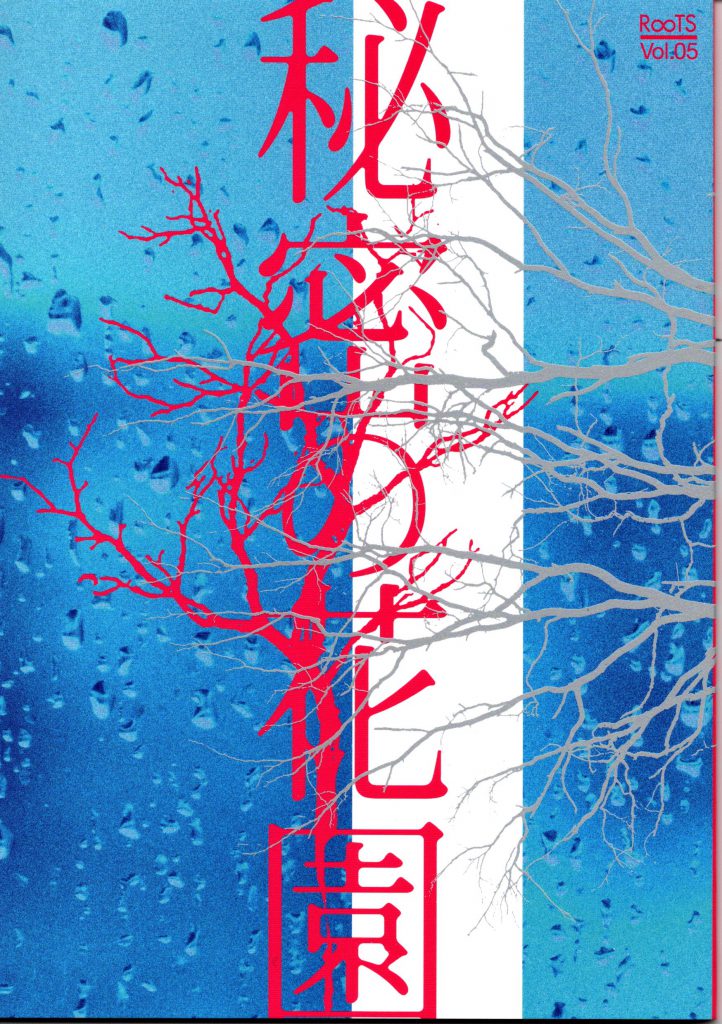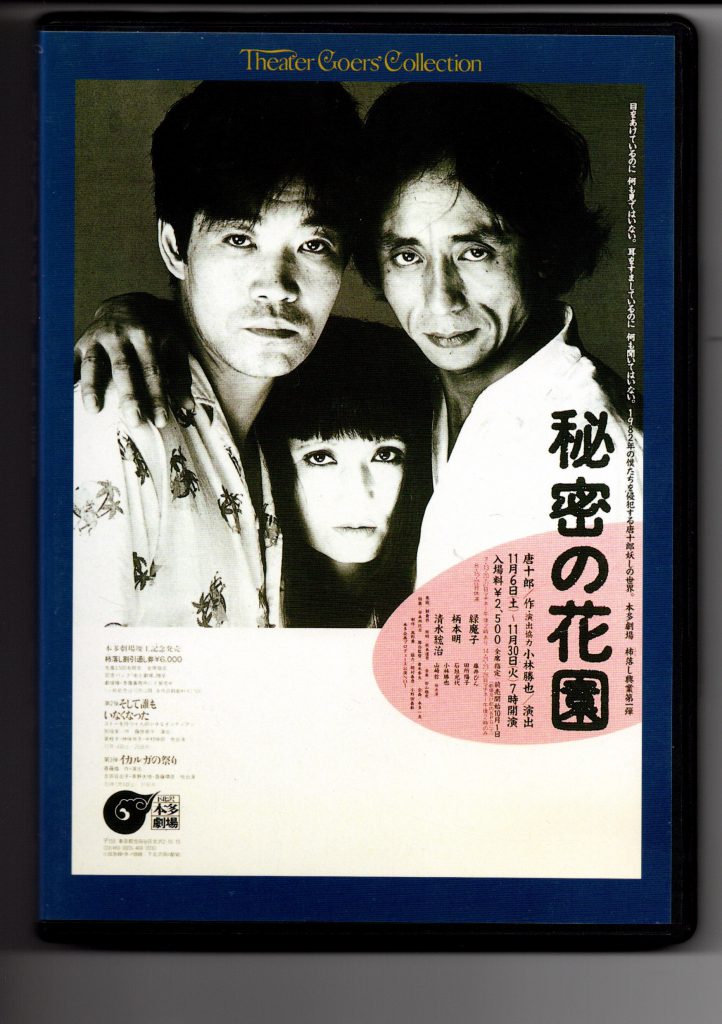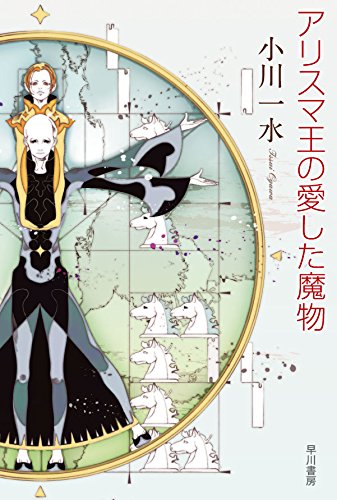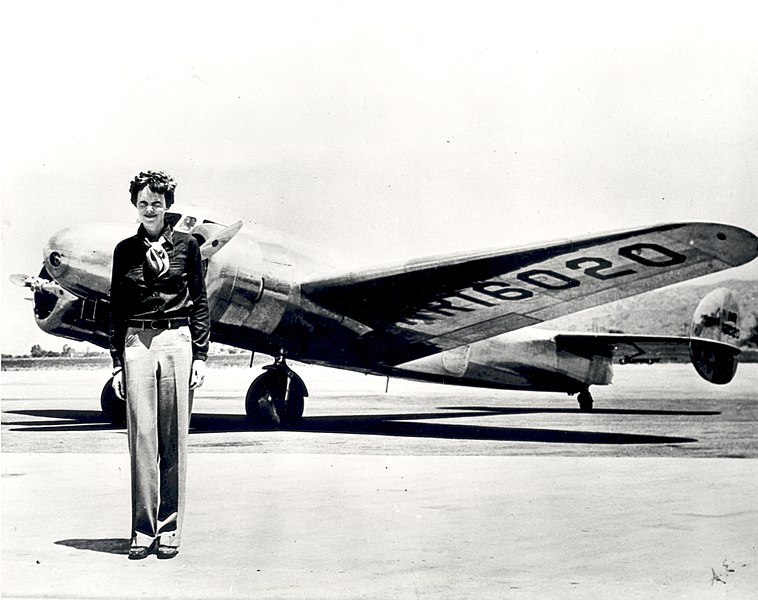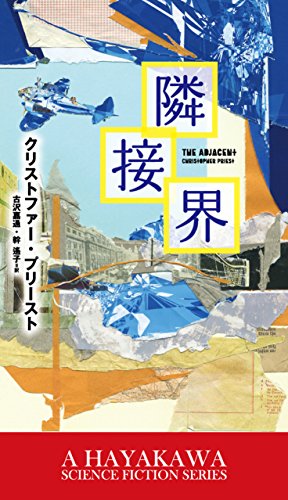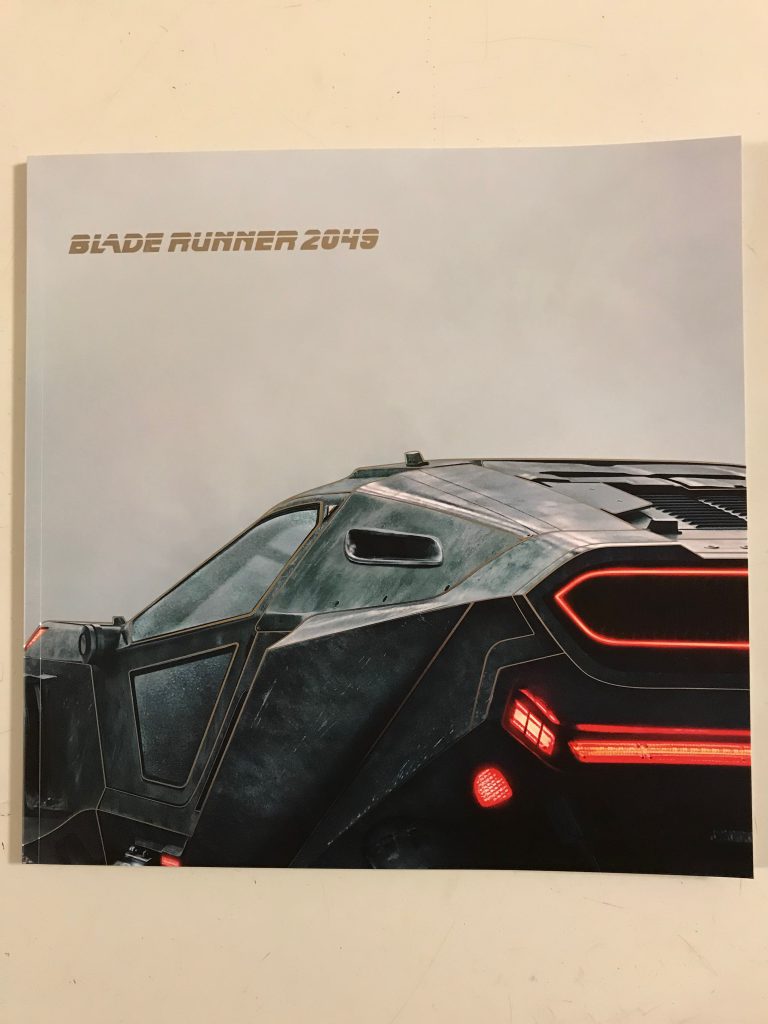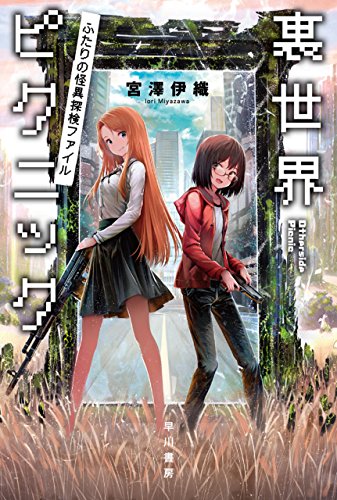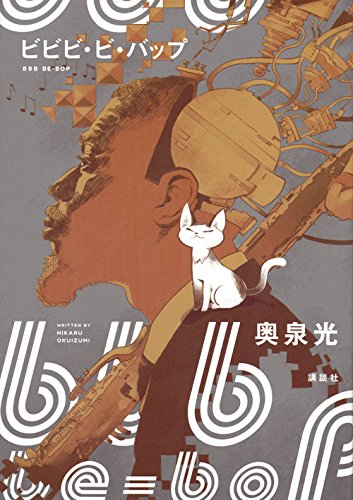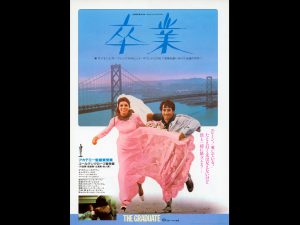個人的に筆者にとっては評価が高いのに、世間一般では忘れ去られてしまった映画を紹介します。1992年のホラー映画「ダスト・デビル」です。2つ前の勤務先、東京船員保険病院(現JCHO東京高輪病院)の当直室で1995年ごろ観たのが最初の出会いでしょう。DVDは未発売ですが、中古で買ったVHSは持っています。
個人的に筆者にとっては評価が高いのに、世間一般では忘れ去られてしまった映画を紹介します。1992年のホラー映画「ダスト・デビル」です。2つ前の勤務先、東京船員保険病院(現JCHO東京高輪病院)の当直室で1995年ごろ観たのが最初の出会いでしょう。DVDは未発売ですが、中古で買ったVHSは持っています。
舞台は、アフリカのナミビア。ナミビア沖では、日本の遠洋マグロ延縄漁船が操業しています。遠隔の地ではあっても、日本との縁はしっかりとある国です。延縄漁の1年半にも及ぶ航海はさぞかし大変なことと想像いたします。
砂漠の悪魔ダスト・デビルが、存在の次元を高めるために猟奇的連続殺人を行うというストーリーです。ナミビアの景勝地でロケをしていて、映画がそのまま観光案内になっているところが特に気に入っています。ナミブ砂漠は、いつかは旅行してみたい憧れの地です。主人公の女性ウェンディが悪魔とともに立ち寄る、ナミビア最南端に位置する大渓谷フィッシュリバー・キャニオンの光景は、TVの画面では残念ながらその迫力が伝わってきません。できることならば映画館のスクリーンで見たかった。
かつてダイアモンド鉱山の拠点として栄えた砂の中に埋もれている街、コールマンスコップのゴーストタウンで、お話はクライマックスを迎えます。超自然の存在から逃れることができるのでしょうか。
コートジボワールに赴任した経験のある古くからの友人に、この映画の話をしたところ、「ナミビアは治安のいい国だ。内戦をやっている国の凄惨さは悪魔の恐怖とは桁が違う」と言われました。確かにそのとおり。