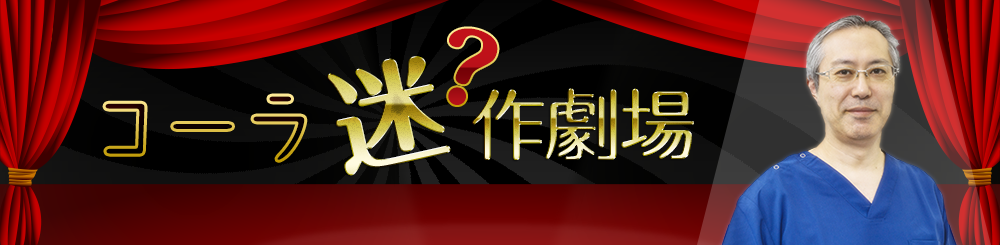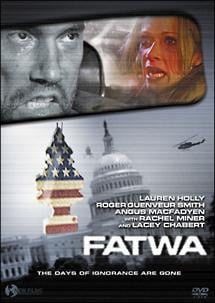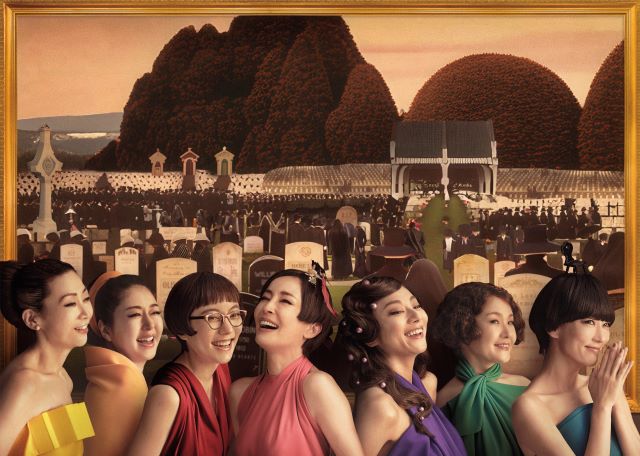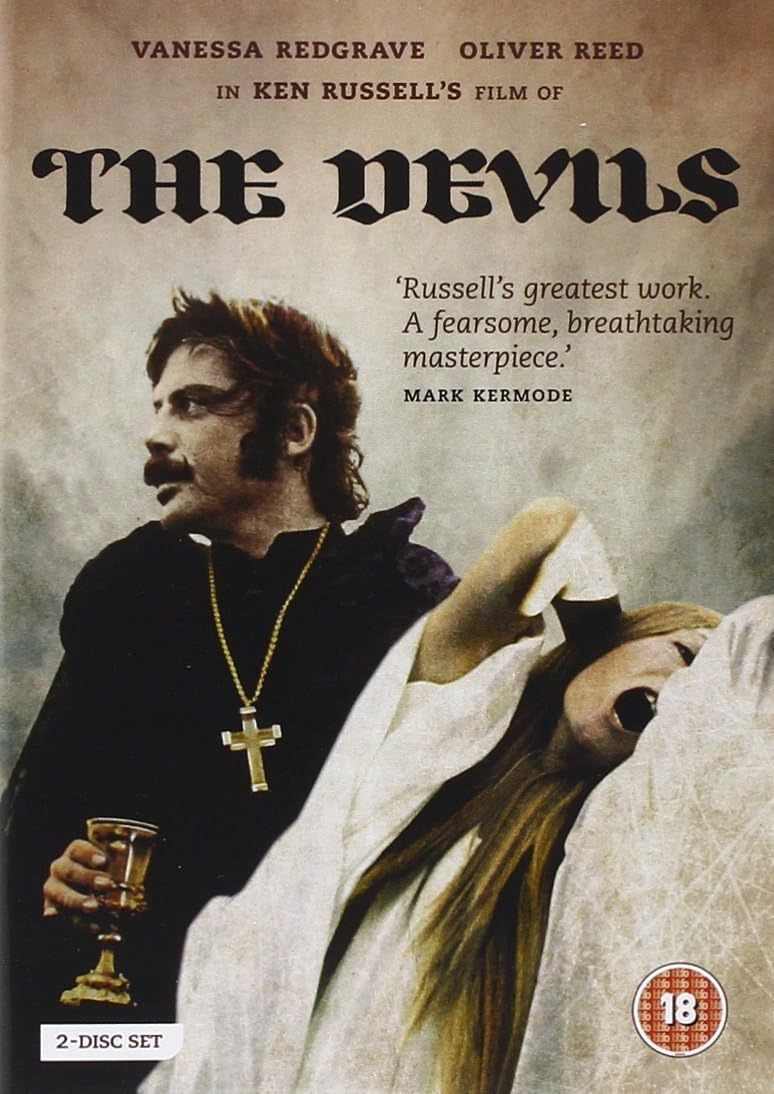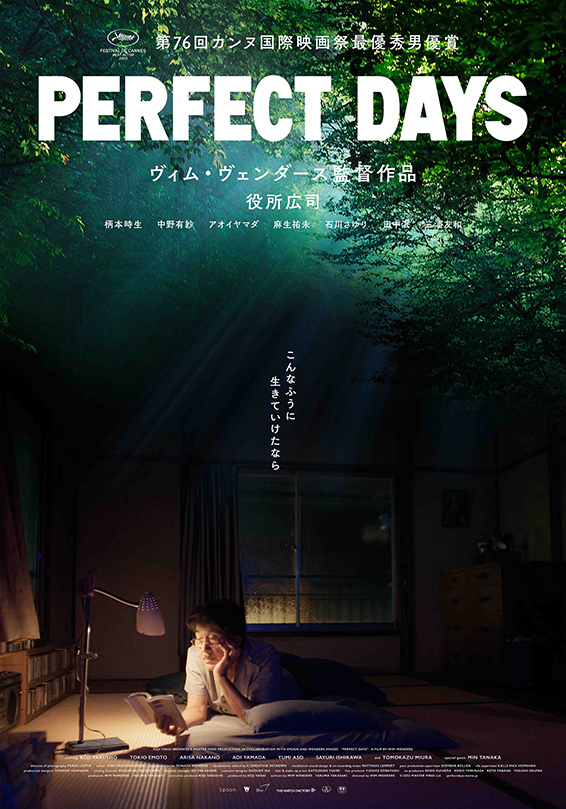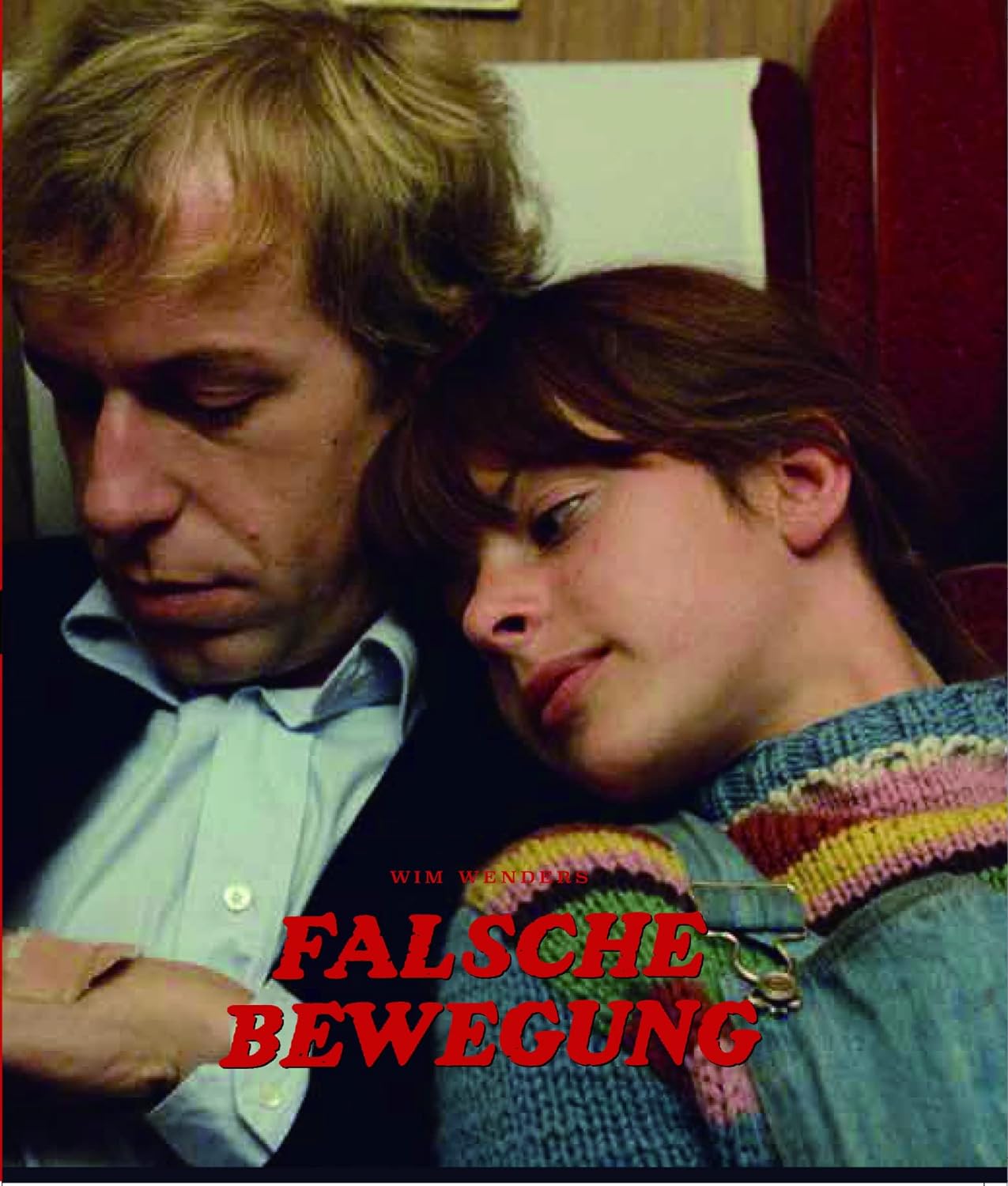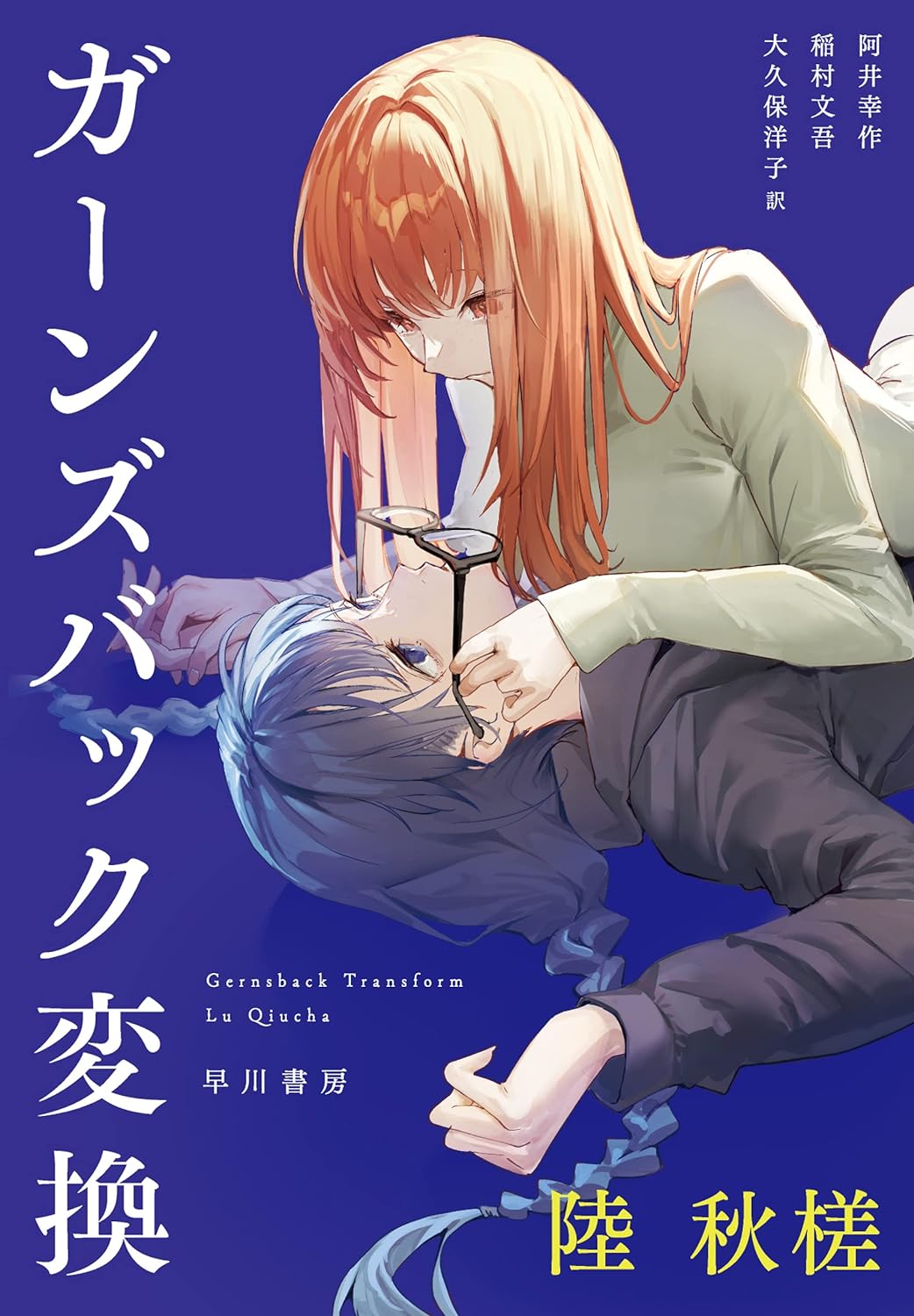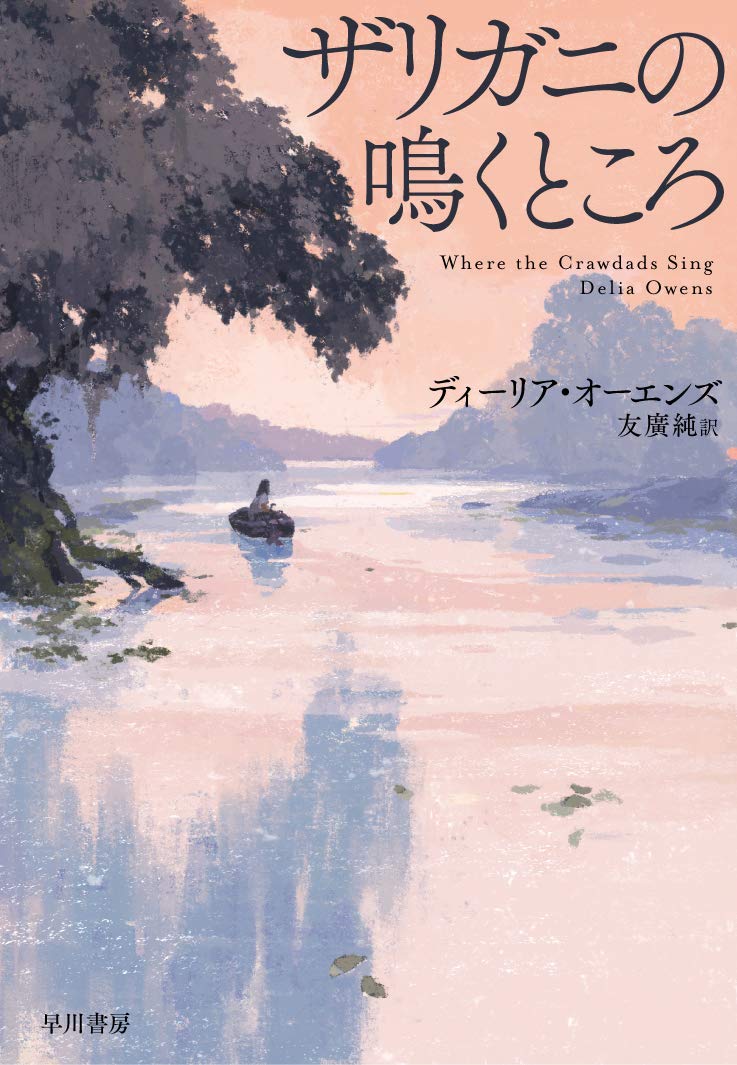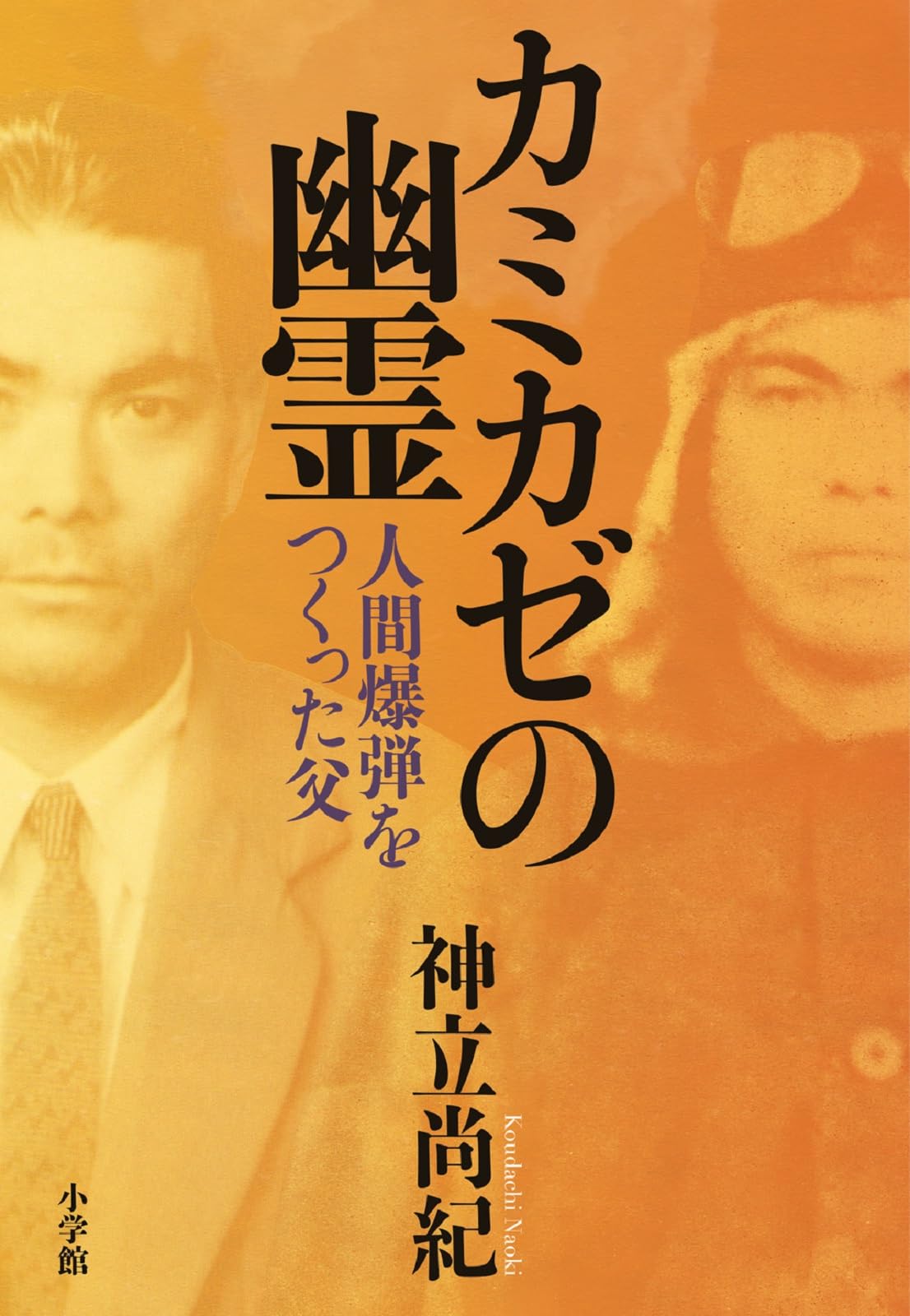ファトゥワとは、イスラム教においてイスラム法学に基づいて発令される裁断。
2006年のほとんど誰にも知られていない、政治サスペンス映画。ジョン・カーター監督。レンタルDVDで観た。意外と面白い。
ローレン・ホリー主演。反テロの中心的役割を務める米国上院議員マギー。夫との仲が冷めきったまま、政治活動で忙しく飛び回っていた。テロリストと夫の親族のギャング双方から、命を狙われることとなる。
「宇宙家族ロビンソン」の、1998年映画版リメイク「ロスト・イン・スペース」で、反抗期の少女である次女のペニーを演じたレイシー・シャベールが、社会に対して反抗期の大学生、マギーの娘の友人ノアを演じる。この方面から、この映画に辿り着いた。