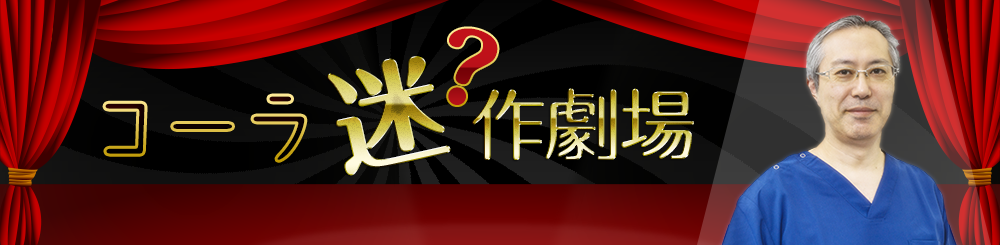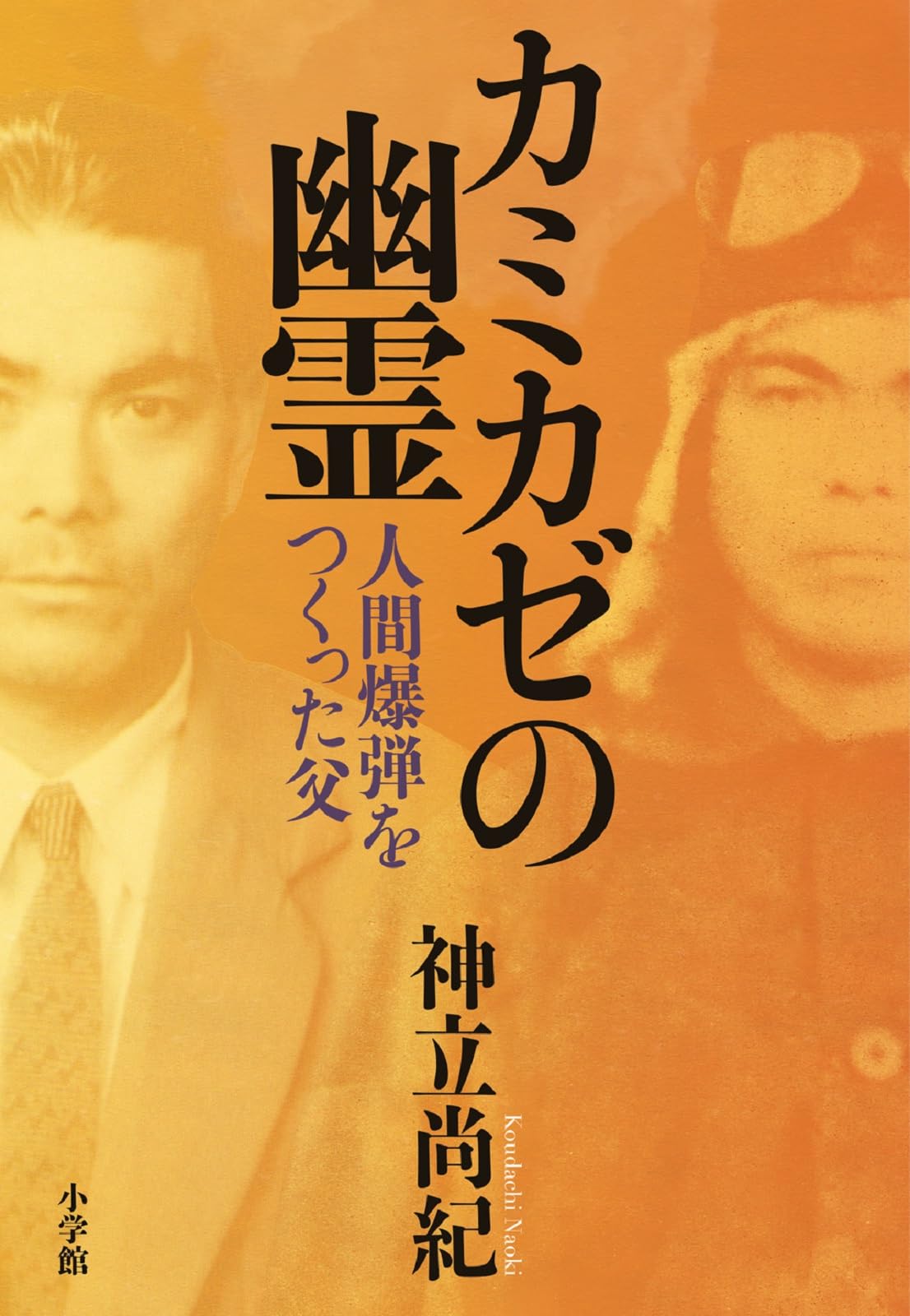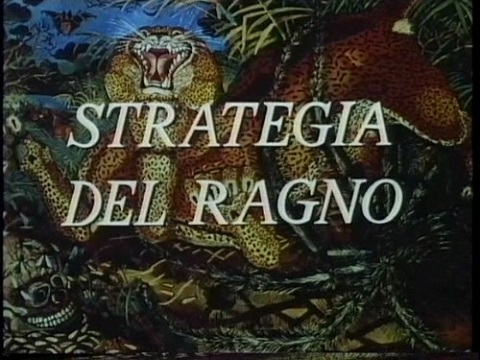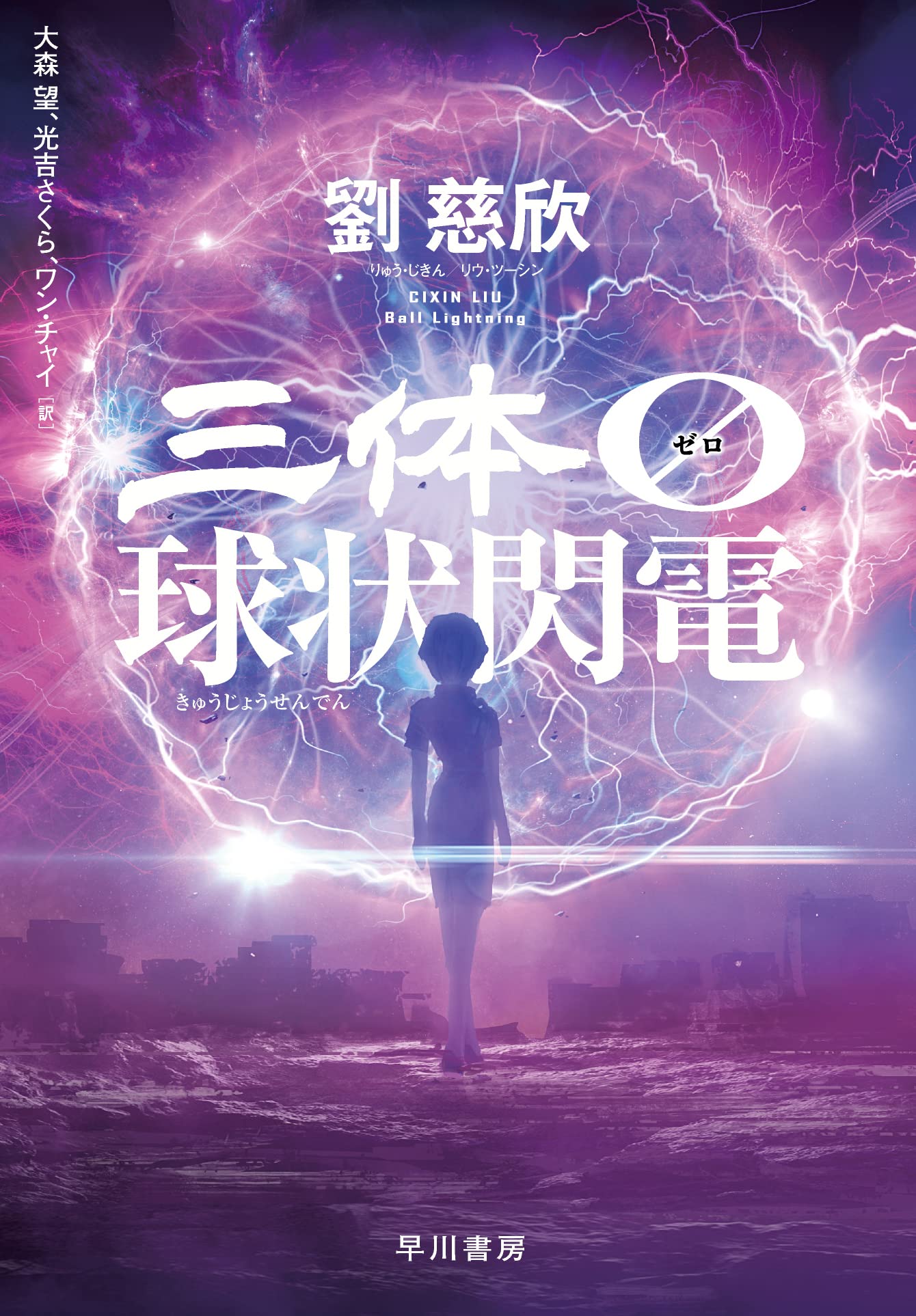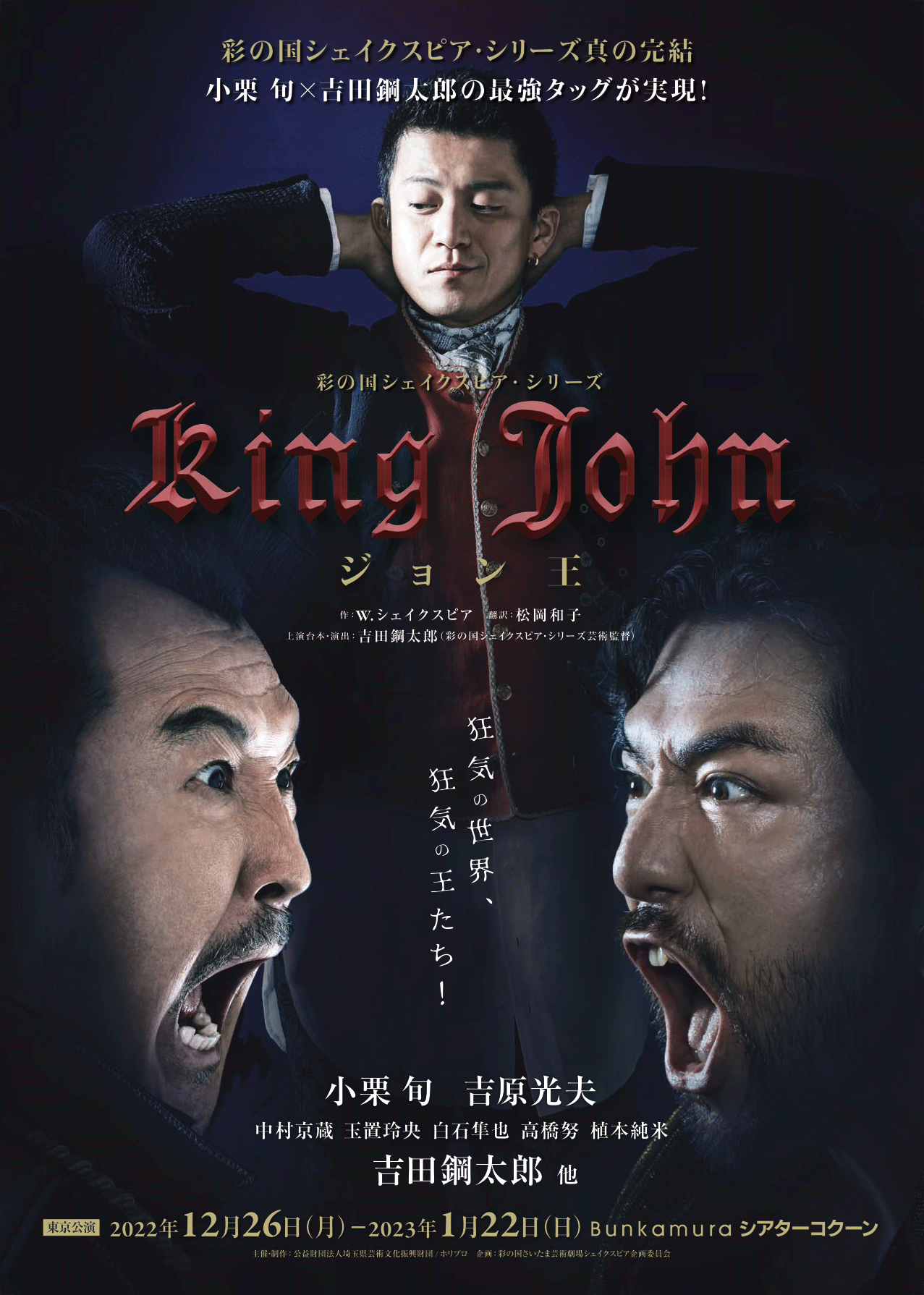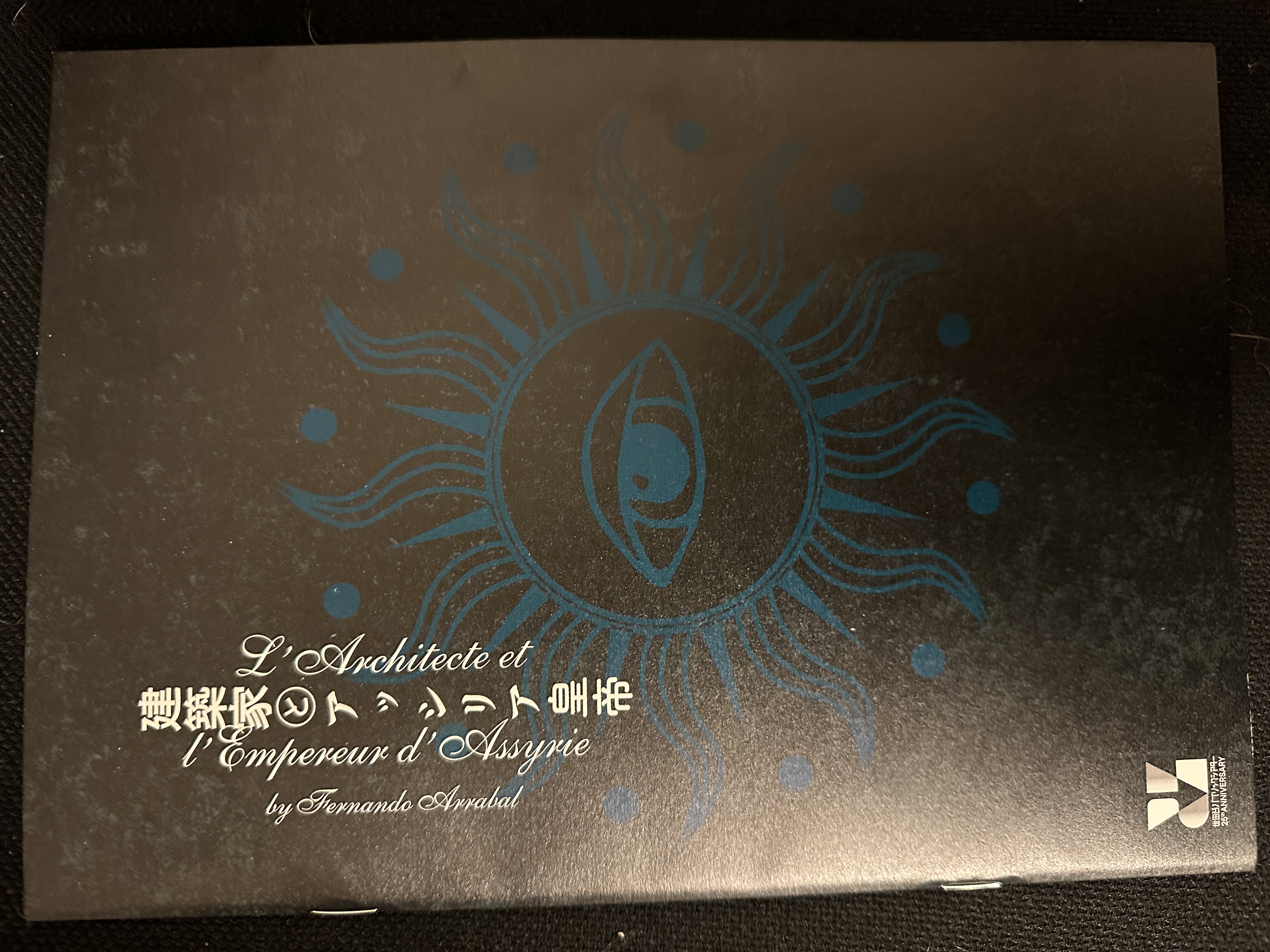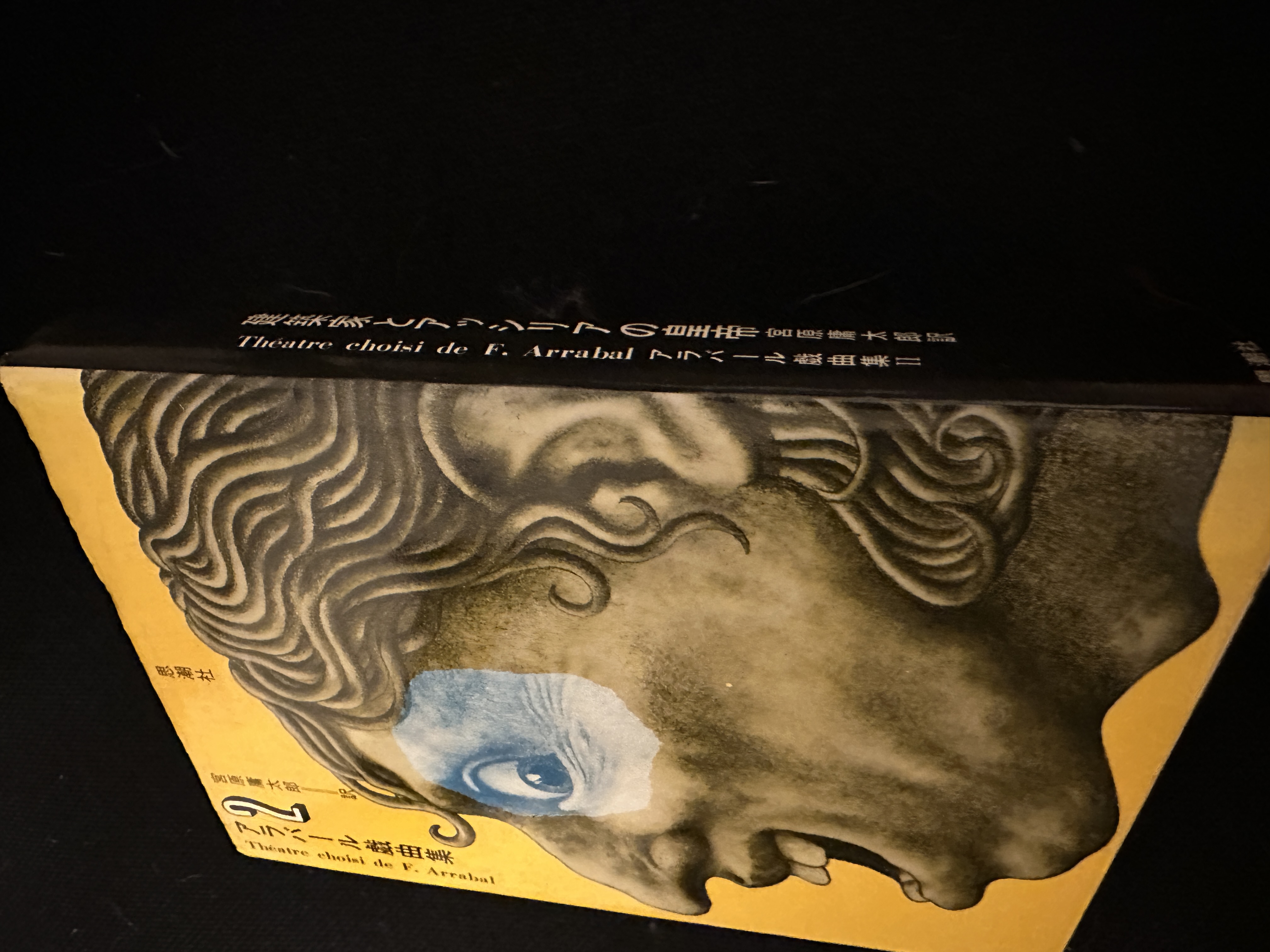古くからの友人が編集者を務めたノンフィクション、「カミカゼの幽霊」を読んだ。
大戦末期の海軍の特攻ロケット機「桜花」。1.2トンの大型爆弾に翼と操縦席とロケットをつけ、一式陸攻に吊るされ敵艦隊のそばまで運ばれ、人間が操縦して敵艦に体当たりする。「人間爆弾」とも呼ばれた。
「桜花」を発案したとされるのはベテランの陸上攻撃機偵察員だった大田正一少尉である。終戦直後、零式練習戦闘機を操縦して姿を消した。自殺飛行とみなされた。
しかし大田は生きていた。戸籍は失ったままで、偽名で結婚し三人の子供をもうけた。
戦局の悪化と共に、特攻はすでに海軍の既定路線となっていた。非人道的な兵器の開発を、上から命じるのではなく、現場の搭乗員からの提案と熱意を受けやむを得ず採用するというスタンスを軍は取りたかったのだろう。
「桜花」の航続距離の短さ、搭載量を超過した一式陸攻の性能低下、護衛戦闘機の数を揃えられなかったことから桜花隊の初出撃では、一式陸攻全機が撃墜された。その後も期待したような戦果を挙げることはできなかった。
蛇足だが、このブログの筆者の父は、材木屋の息子の飛行機設計技師だった。木製の特攻機の開発を命じられていたのではないかと想像するが、特攻に関して戦後まったく触れることはなかった。