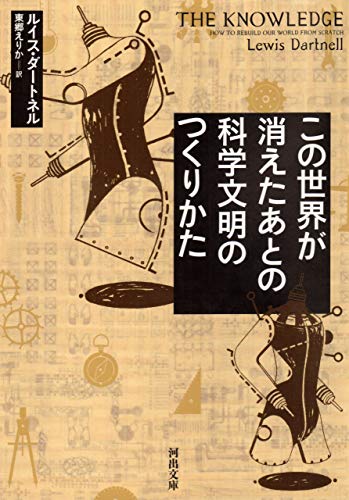「二〇一九年末、世界は未曽有のパンデミックにみまわれた。そのウイルスはエボラ出血熱を上回る致死率と激烈な感染力を特徴とし、しかもひんぱんに変異してワクチン開発の努力をあざ笑った。ついに人類は降参し、社会性哺乳類特有の密になる習性を捨て去ることにした。のちにいう「都市撤退宣言」が出されたのである。」
この背景を持つ世界を描いた上記短編集の6つ目の話、「みんな、どこにいるんだ」の内容に触れる。
筆者のもっとも好きな寿司ねたはタコだ。タコせんべいも、子供の頃駄菓子屋で買う定番のおやつだった。アニメ「ぼざろ」の影響を受け、江ノ島のタコせんべいをオンラインで購入し、ご近所に配ったりしている。
 ピーター・ゴドフリー=スミスの「タコの心身問題」を読んでいるだろうか。タコは非常に賢い無脊椎動物である。ごく普通のマダコの身体には、合計で約5億個のニューロンがある、これは無脊椎動物の中では群を抜いている。タコの脳は脊椎動物の脳とはまったく違う。持っているニューロンの大半が脳の中に集まっているわけではなく、ニューロンの多くは腕の中にあるのだ。
ピーター・ゴドフリー=スミスの「タコの心身問題」を読んでいるだろうか。タコは非常に賢い無脊椎動物である。ごく普通のマダコの身体には、合計で約5億個のニューロンがある、これは無脊椎動物の中では群を抜いている。タコの脳は脊椎動物の脳とはまったく違う。持っているニューロンの大半が脳の中に集まっているわけではなく、ニューロンの多くは腕の中にあるのだ。
現実世界では、知性の高い動物の狩猟を禁じる国際的な運動が、クジラのようにタコも守ろうとしている。高齢の日本人グループが、タコ焼きの美味しさの思い出を懐かしく語り合うという未来がやってくるのだろうか。
「みんな、どこにいるんだ」では、ある年の2月29日にタコが道具を使って人間の文字で、「ワタシタチヲ タベナイデ」と世界中で訴えたことが、事件の始まりだった。