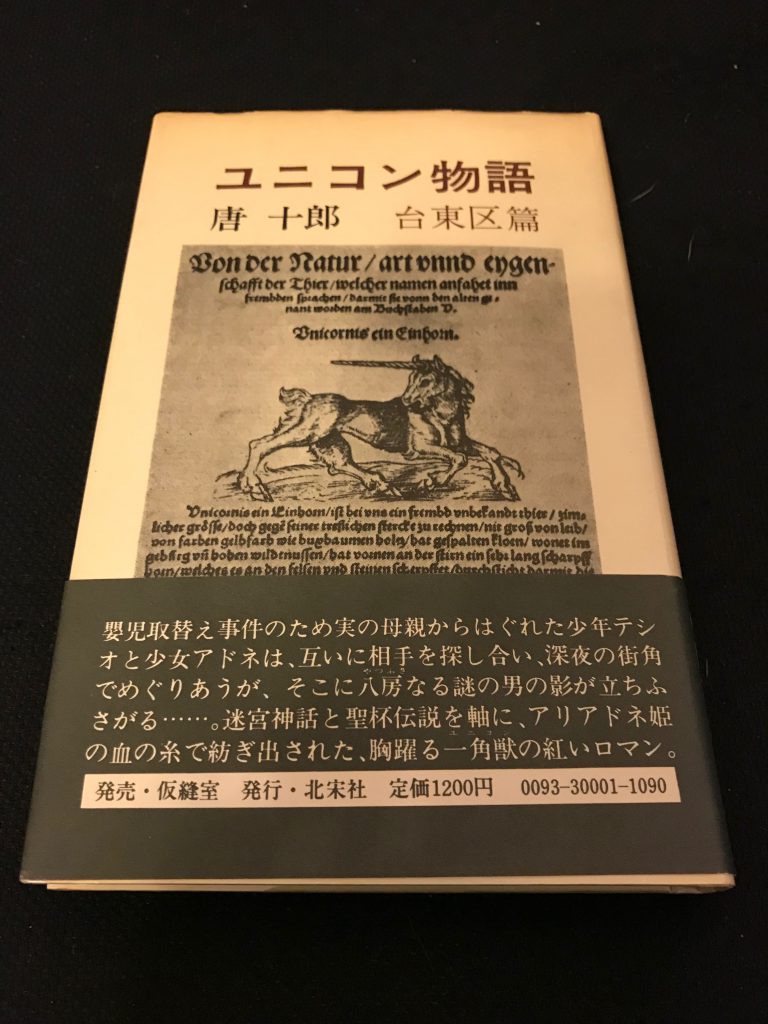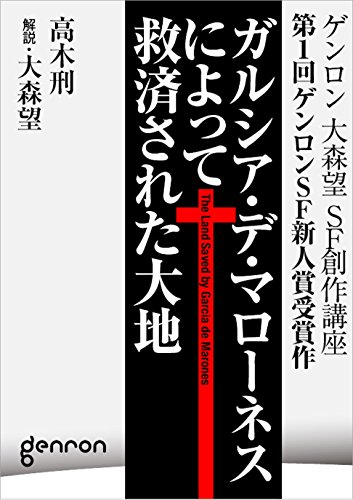とにかく面白い。サメについて、生物学的にも水産資源としても興味を満たしてくれる。作者の実体験を含めて、多面的なサメ話が語られる。
とにかく面白い。サメについて、生物学的にも水産資源としても興味を満たしてくれる。作者の実体験を含めて、多面的なサメ話が語られる。
2018年5月10日の発行日の前に予約注文して、発行日に手に入れ2日間ほどで読了していたのだが、クリニックのスタッフに貸し出していたため、このブログで紹介するのが遅くなってしまった。
人食いザメというものは、映画「ジョーズ」で植え込まれた誤解であることが、最初に記されている。サメは殺し屋の悪役ではなく、臆病な愛おしい生き物であると。
生物学的知識としては、普通の魚が硬骨魚類であるのに対し、サメとエイは軟骨魚類に属すこと。胎生のサメが7割で、さらに多様な繁殖形態に分類できることなど、いろいろなことが勉強できた。
私の記憶では、昭和30年代、東京の庶民の食卓によくサメ肉の料理がのぼった。決して一部の地域に限定されて食べられている食材ではない。水産資源としてのサメの話、サメ料理の話も盛りだくさんである。作者が、サメを愛するあまり、サメを絶対に殺してはいけないなどと言い出すことはないところがいい。
水族館は私の好きなスポットだが、2016年11月に大洗水族館に行ったのが最後となっている。このときはタコばかり見ていた。基礎知識を豊富に仕入れたので、これからはサメもじっくりと見ることができる。