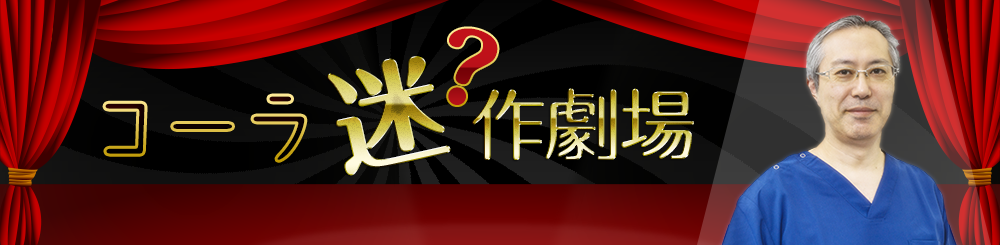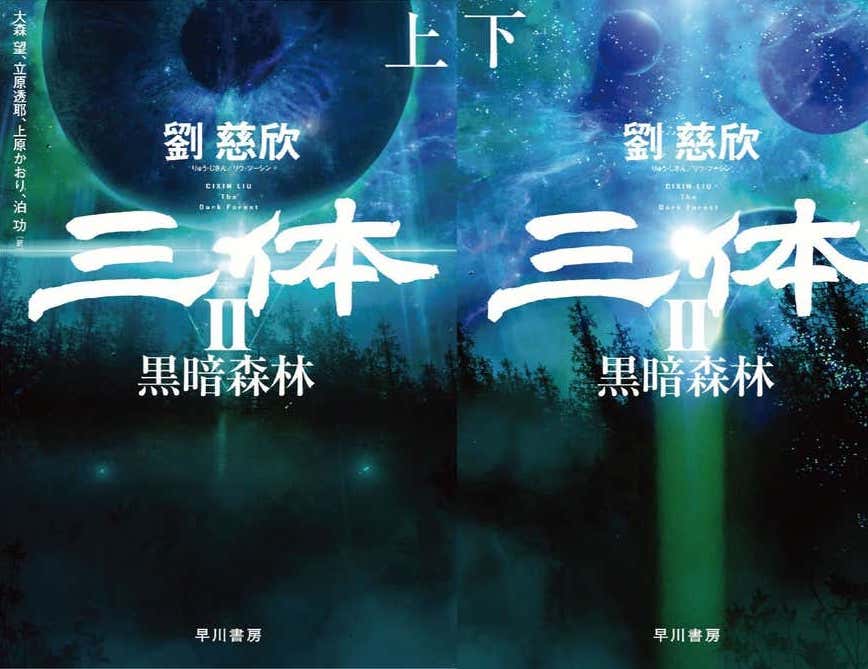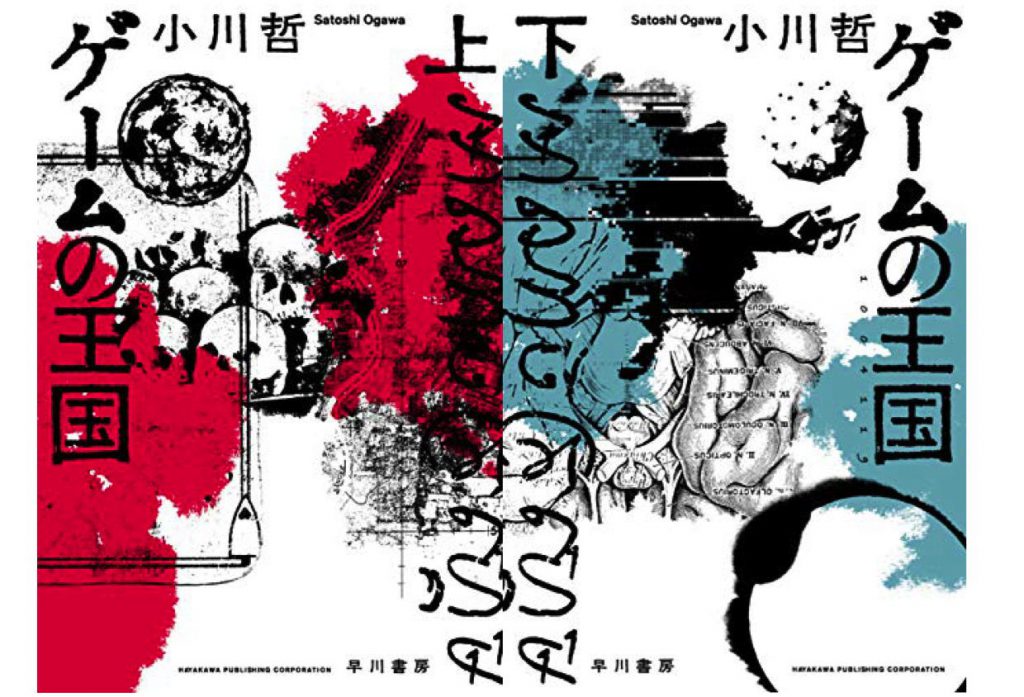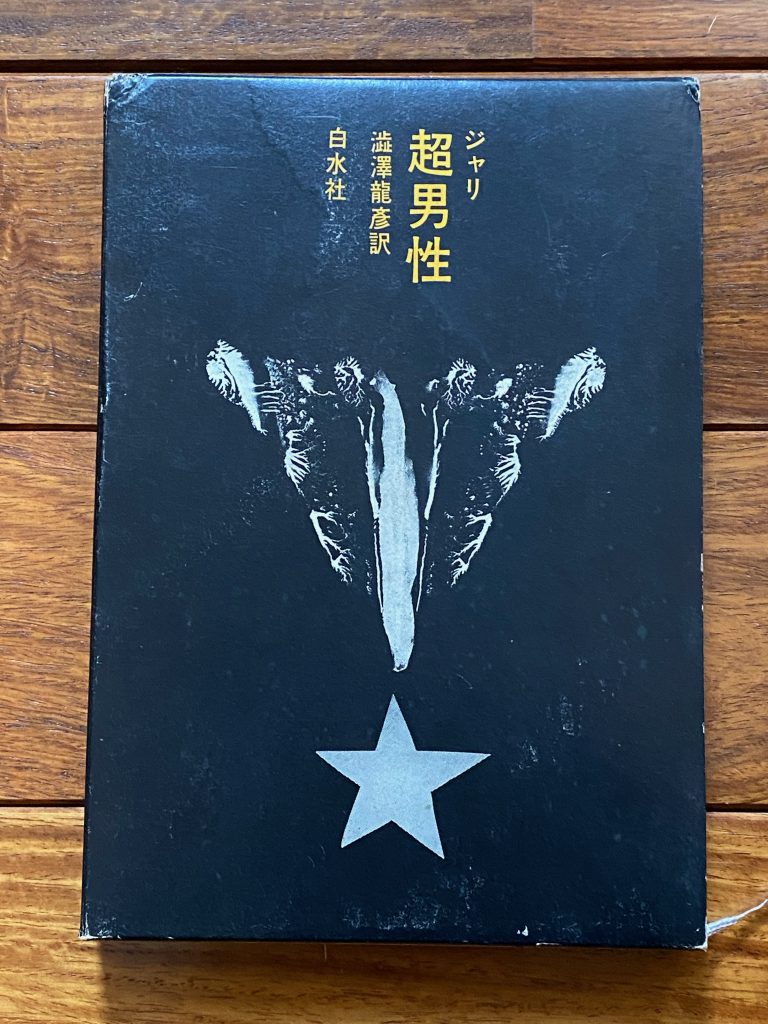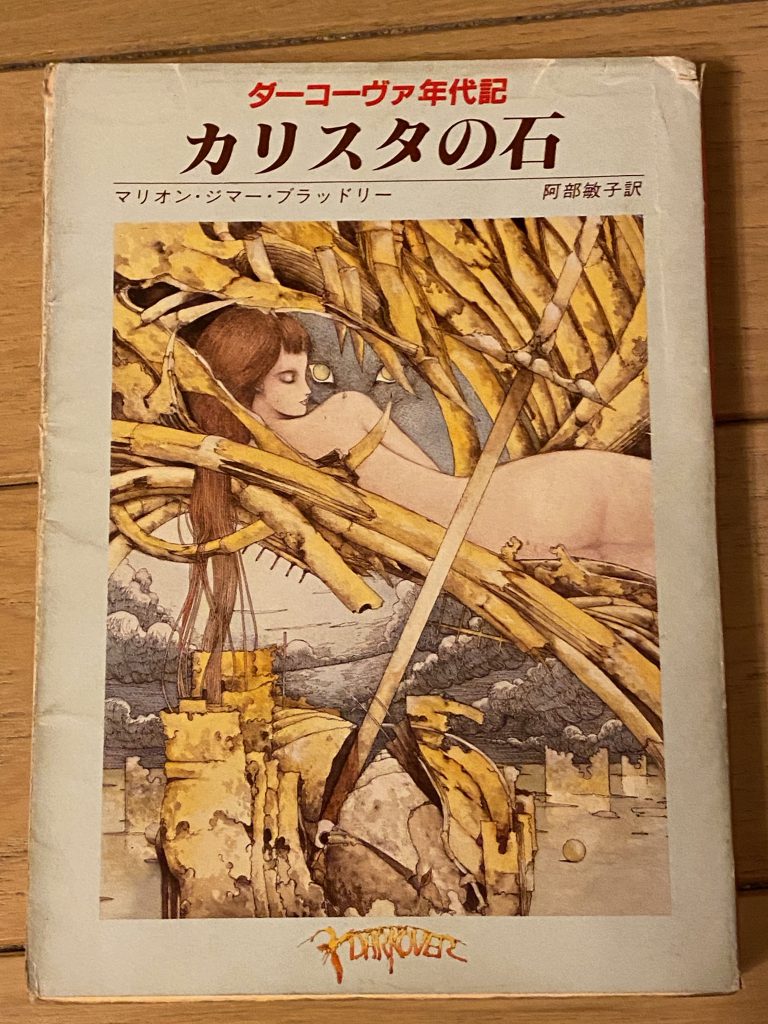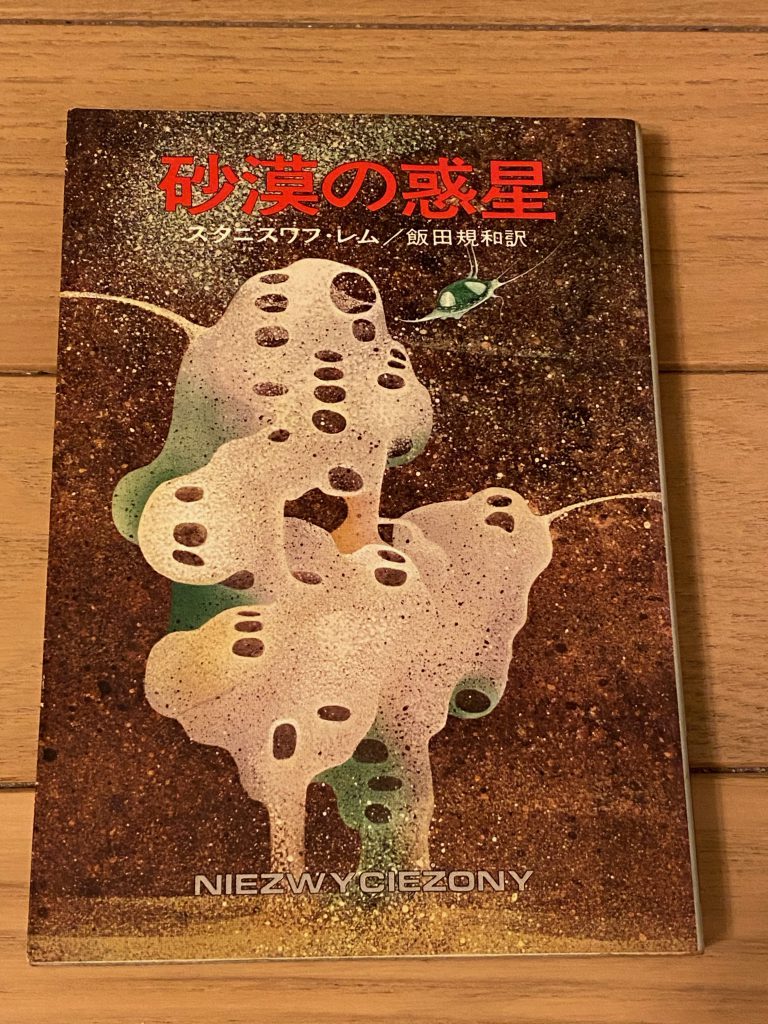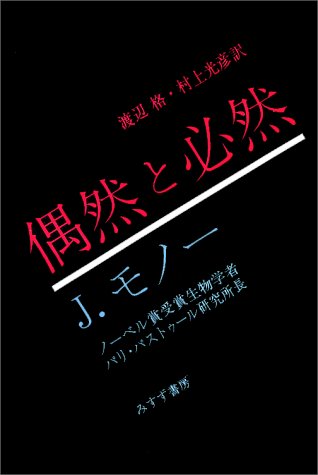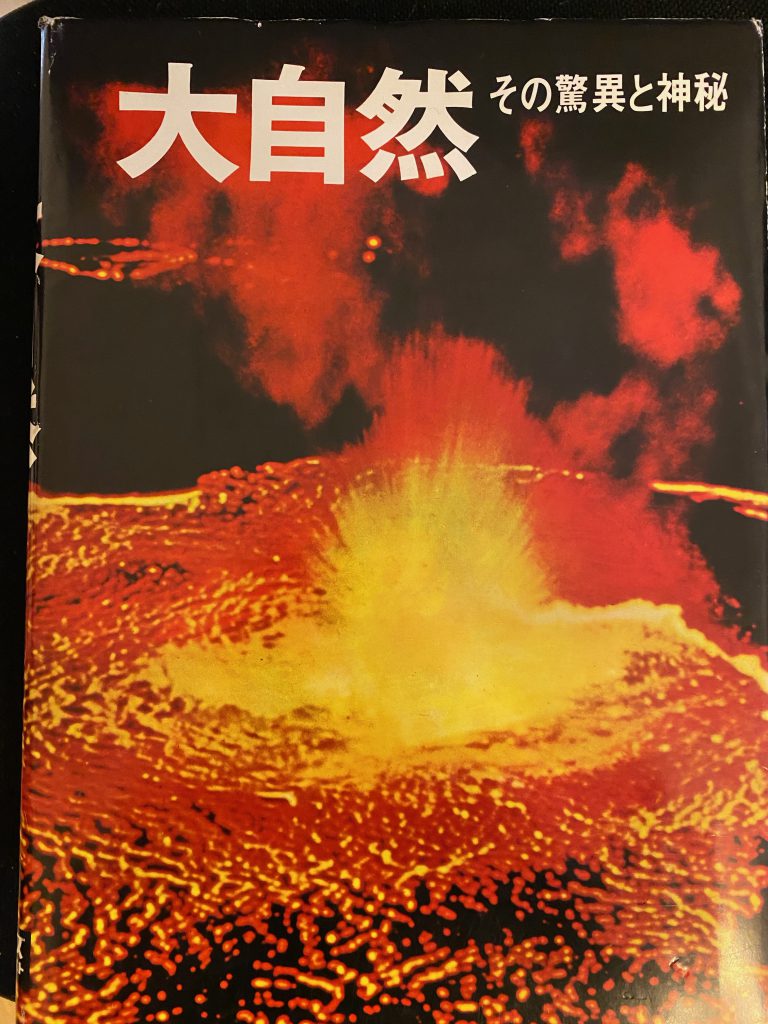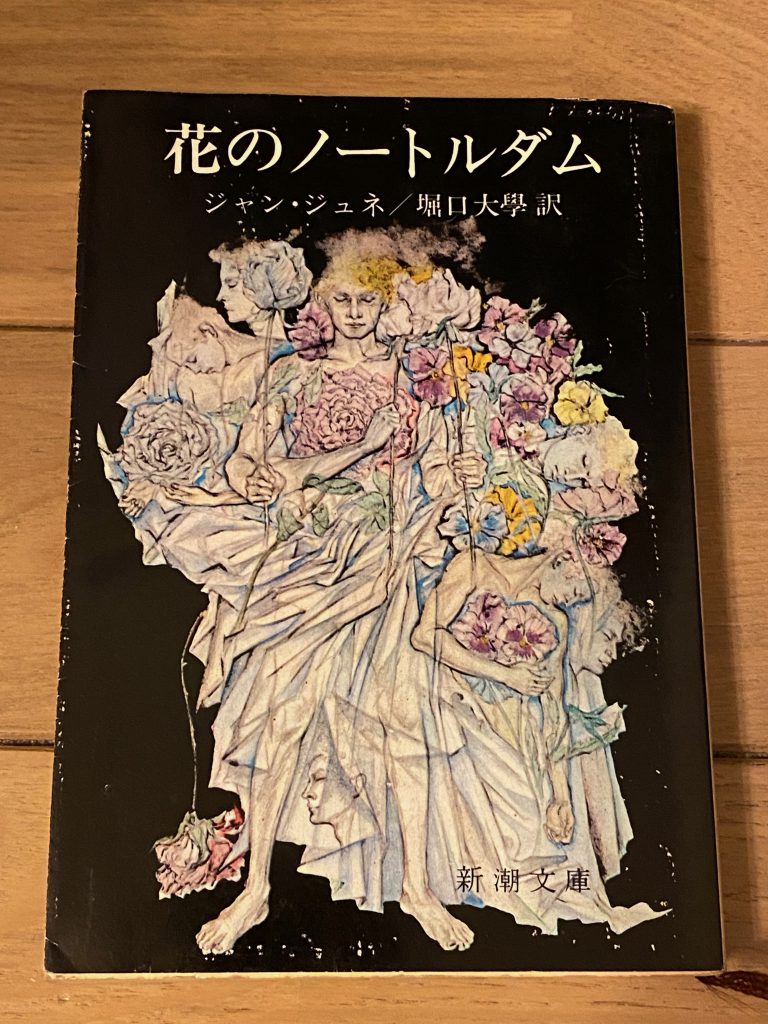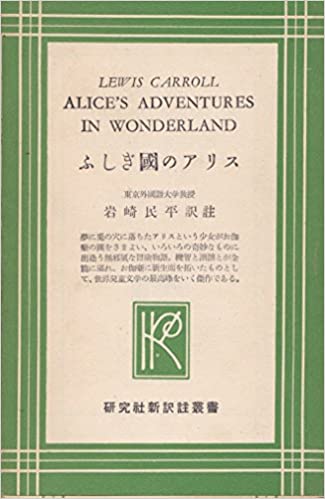三浦春馬を偲ぶため、中古DVDで映画「ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ」を見直した。舞台「ZIPANG PUNK〜五右衛門ロックIII」シアターオーブ(2013.1観劇)や、映画「永遠の0」(2014.1鑑賞)はまだ記憶に比較的しっかりと残っていたが、本作は映画館で2008.2に観たきり忘れていた。
三浦春馬を偲ぶため、中古DVDで映画「ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ」を見直した。舞台「ZIPANG PUNK〜五右衛門ロックIII」シアターオーブ(2013.1観劇)や、映画「永遠の0」(2014.1鑑賞)はまだ記憶に比較的しっかりと残っていたが、本作は映画館で2008.2に観たきり忘れていた。
原作は「NHKにようこそ!」で有名になった元ひきこもり作家、滝本竜彦のデビュー作だ。2001年発売で、2002年に読んでいる。
長編映画のメガホンを取るのは初めての、北村拓司が監督である。
映画の内容は原作とほぼ同じで、絵里の制服はセーラー服ではなくブレザー。へたれな高校生山本陽介(市原隼人)は、チェーンソーを振り回す怪人との死闘を繰り返している美少女高校生、雪崎絵里(関めぐみ)と出会った。チェーンソー男が出現したときから、驚異的な身体能力が芽生えた絵里だったが、陽介は常人のままでまったく戦力にならず後ろで応援しているだけ。しかし、陽介の粘りから、二人で行動をともにすることは続いていった。
バイクで夜間暴走し死亡した、陽介の同級生の友人、能登を三浦春馬が演じた。12年前の映画なので、撮影時は17歳か18歳か。とにかく若い。永遠に陽介の先を走り続け、追いつくことのできない男の位置づけだ。
「無理だよお前は。あの子とダラダラと薄らぼんやりとした幸せを楽しめよ」
「なぁ能登!」「生きているオレが羨ましいだろう!」